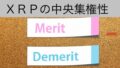ビットコインの価値がピンとこない人のために、2分で読める記事です。
日本に住んでいると、既存のお金(法定通貨)に不便を感じることは少ないかもしれませんが、全世界では既存の法定通貨には不都合・不便が多くあります。
ビットコインの価値を理解するには、日本における常識から離れた方がいいかもしれません。
ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれる理由、開発目的、機能を記載します。
1. ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれる理由
ビットコインがデジタルゴールドと呼ばれるのは、以下のような金(ゴールド)との共通点があるためです:
希少性
ビットコインの総供給量は2,100万枚に制限されており、新規発行はマイニングを通じて徐々に減少し、2140年頃に上限に達します。これは金の埋蔵量が有限である点に似ています。この希少性が、価値の保存手段としての魅力を高めます。
価値の保存(Store of Value)
金はインフレや経済危機に対して価値を保つ資産として長い歴史があります。ビットコインも、中央銀行や政府の管理を受けない非中央集権的な性質から、法定通貨の価値下落や金融システムの不安定さに対するヘッジとして機能すると考えられています。
耐久性
金は物理的に腐食せず、長期間価値を保持します。ビットコインもデジタル資産として、ブロックチェーン上に記録される限り消失や劣化しません。
分割可能性
金は小さく分割して取引可能ですが、ビットコインも1BTCを1億分の1(1サトシ)まで分割でき、柔軟な取引が可能です。
移動の容易さ
金は物理的な移動にコストと時間がかかりますが、ビットコインはインターネット上で瞬時に国境を越えて送金可能です。この点で、ビットコインは「デジタル」なゴールドとして優れています。
市場の認識
投資家やアナリストの間で、ビットコインは金のような安全資産としての役割を担う可能性があると見なされており、特にインフレ懸念や金融危機時に注目されます。例えば、2020年のコロナ危機や2022年のウクライナ危機時に、ビットコインへの投資需要が急増しました。
ただし、ビットコインは金の完全な代替ではなく、価格のボラティリティが高いことや、法的な規制リスクがある点で異なります。それでも、「デジタルゴールド」という呼称は、その希少性と価値保存の可能性を象徴しています。
2. ビットコインの開発目的
ビットコインは2008年にサトシ・ナカモト(匿名人物またはグループ)によって提案され、2009年に運用開始されました。開発の背景と目的は以下の通りです:
金融システムへの不信感
2008年のリーマンショックで、銀行や中央銀行の不透明な運営や過剰な通貨発行が世界経済に大打撃を与えました。サトシ・ナカモトは、中央機関に依存せず、信頼できる金融システムを構築することを目指しました。
非中央集権型の通貨
ビットコインは、中央銀行や政府の管理を受けない分散型通貨として設計されました。ブロックチェーン技術を用いて、取引はピア・トゥ・ピア(P2P)で直接行われ、第三者の仲介を排除します。
透明性と信頼性の確保
ビットコインの取引は公開された台帳(ブロックチェーン)に記録され、誰でも検証可能です。これにより、改ざんや不正が極めて困難になり、信頼性が確保されます。
金融包摂
金融包摂(きんゆうほうせつ)とは、すべての人が経済活動に必要な金融サービス(預金、送金、融資、保険など)を利用できるようにする取り組みのこと。
ビットコインは銀行口座を持たない人々や、従来の金融システムにアクセスできない地域の人々に、インターネットさえあれば利用可能な通貨を提供することを目指しました。
インフレ対策
ビットコインの供給量はプログラムで固定されており、過剰な通貨発行によるインフレを防ぐ設計です。
これは、中央銀行が通貨を無制限に印刷するリスクへの対抗策です。
サトシ・ナカモトのホワイトペーパー(2008年)では、ビットコインは「信頼できる第三者を必要としない電子キャッシュシステム」と定義されており、個人間の直接取引を可能にすることを主眼としています。
(ホワイトペーパーとは、暗号資産プロジェクトの詳細を説明する文書で、プロジェクトの目的、技術、ビジネスモデル、トークンなどについて記載されている)
3. ビットコインの主な機能
ビットコインは通貨、技術、資産としての多様な機能を持っています。以下に主要な機能を説明します:
デジタル通貨としての機能
・送金:ビットコインは国境を越えた送金が迅速かつ低コストで可能です。銀行や送金業者を介さず、ウォレット間で直接取引できます。
・マイクロペイメント:1サトシ(0.00000001 BTC)単位での少額送金が可能で、小規模な取引にも対応。
・ピア・トゥ・ピア取引:中央管理者がいないため、ユーザー同士が直接取引でき、仲介手数料が不要。
価値の保存(Store of Value)
・ 固定供給量と半減期(約4年ごとにマイニング*報酬が半減)により、インフレ耐性があるとされます。投資家は長期的な資産保有手段として利用。
例:2020年以降、MicroStrategyやTeslaなどの企業がビットコインを財務資産として保有。
(*マイニングとは、暗号資産の取引などのデータをブロックチェーンに保存する作業を行い、その報酬として暗号資産を得る行為のこと)
分散型ネットワーク
ビットコインは世界中のノード(コンピュータ)で運用される分散型ネットワークで稼働。単一障害点がなく、システムダウンや検閲が困難。
マイニングによるコンセンサス(Proof of Work)で、取引の正当性を検証し、ネットワークのセキュリティを維持。
透明性と匿名性
取引はブロックチェーンに公開され、誰でも閲覧可能。ただし、ウォレットアドレスは匿名(実名と直接紐づかない)で、プライバシーを一定程度保護。
ただし、取引追跡技術の進化により、完全な匿名性は保証されない場合も。
プログラマブルな機能
ビットコインのスクリプト言語により、スマートコントラクトの基本的な機能(例:マルチシグネチャやタイムロック)を実現。
例:Lightning Networkは、ビットコインのスケーラビリティを向上させる第二層ソリューション。
(ただし、イーサリアムのような高度なスマートコントラクトには対応しない。)
耐検閲性
政府や企業による取引の凍結や制限が困難。政治的に不安定な地域や、検閲の厳しい国での資産保護に利用される例も(例:ベネズエラ、ジンバブエ)。
4. 補足:ビットコインの課題と進化
ビットコインには以下のような課題もありますが、技術的な進化で改善が図られています:
スケーラビリティ
1秒あたり約7件の取引処理能力は、Visaなどのシステムに比べ低い。Lightning Networkなどのソリューションで高速化が進む。
エネルギー消費
Proof of Workによるマイニングは大量の電力を消費。再生可能エネルギーの利用や効率化が議論されている。
価格の不安定性
投機的な取引により価格が大きく変動。長期的な安定性には課題が残る。
5. まとめ
・デジタルゴールドと呼ばれる理由は、希少性、価値保存、耐久性、分割可能性、移動の容易さにより、金に似た特性を持つから
・そもそもの開発目的は中央機関に依存しない、透明で信頼性の高い電子キャッシュシステムの構築。金融危機への対抗と金融包摂を目指す。
・機能は、送金、価値保存、分散型ネットワーク、透明性、耐検閲性など、多様な用途に対応。